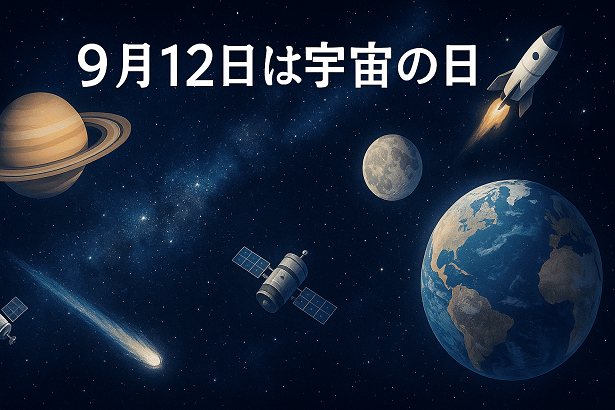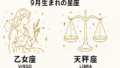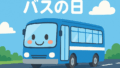「宇宙の日ってよく聞くけど、どうして9月12日なの?」「子どもに説明したいけど由来がわからない」「イベントや雑学も一緒に知りたい」──こんなお悩みを解決します。
■本記事でわかること
- 宇宙の日の意味・由来と制定の背景
- 各地で開催されるイベントや行事の内容
- ビジネス雑談や豆知識に役立つ宇宙の雑学
■本記事の信頼性
本記事は、JAXAや各科学館の公式情報をもとにリサーチし、さらに宇宙飛行士・毛利衛さんのエピソードも交えて解説しています。初心者でも理解しやすいように整理しているので安心してお読みいただけます。
この記事を読み終えた後には、「宇宙の日ってこういう日なんだ!」と自信を持って人に説明できるようになり、イベントや雑学を楽しみながら周囲との会話にも活かせるようになりますよ。
「宇宙の日」とは?意味と由来
いつ・誰が決めたの?
「宇宙の日」は1992年に文部省(現在の文部科学省)と宇宙開発事業団(NASDA、現在のJAXA)が制定しました。目的は、日本国民に宇宙への関心を深めてもらい、次世代を担う子どもたちに科学技術の夢を与えることでした。
当時の日本はバブル崩壊後の不況に入りつつありましたが、宇宙開発に関しては国民的な期待が高まっていました。人工衛星の打ち上げや宇宙ステーション計画への参加など、日本の宇宙技術は着実に進展しており、「宇宙を自分たちの生活とつなげて考える文化」を根付かせる狙いがあったのです。
また、国際的に見ても、記念日を設けて宇宙を身近に感じてもらう取り組みは世界各国で行われていました。日本でも同様に「国民と宇宙をつなぐ特別な日」を必要としていたのです。
この背景から、文部省とNASDAは合同で「宇宙の日」を設け、毎年全国で教育イベントや科学館の展示を行うことを決めました。つまり「宇宙の日」は国の機関が主導して作った、正式な記念日なのです。
なぜ9月12日なの?日付の由来
9月12日という日付は偶然ではなく、はっきりした根拠があります。1992年9月12日、宇宙飛行士の毛利衛さんがスペースシャトル「エンデバー号」に搭乗し、日本人として初めて本格的な宇宙実験を行ったのです。
この出来事は、日本の宇宙開発にとって大きな転機でした。それまでの日本人宇宙飛行士は、あくまでソ連やアメリカの計画に「乗せてもらう」形で参加していました。しかし毛利さんのミッションは、日本独自の実験機材を持ち込み、日本の科学者たちが立案したテーマで実験を行うものでした。
つまり、9月12日は「日本が独自に宇宙研究を行った最初の日」と言えるのです。だからこそ、この日が「宇宙の日」と定められました。
さらに豆知識として、国際的には1961年4月12日が「人類初の宇宙飛行の日(ユーリイ・ガガーリンが宇宙へ行った日)」として有名です。日本はそれに倣い、ガガーリンの偉業からちょうど30年後の節目に、自国の挑戦を記念する日を設けたとも言えます。
毛利衛さんとJAXAの貢献
毛利衛さんは北海道余市町出身で、もともとは科学者として研究活動を行っていました。1985年に日本人初の宇宙飛行士候補に選ばれ、7年間の厳しい訓練を経てついに宇宙へ。1992年のSTS-47ミッションでは、微小重力環境での材料実験や生命科学実験など、合計43の実験を行いました。
この実験は「ふわっと’92」と呼ばれ、日本中の研究者や学生が参加したプロジェクトでした。たとえば「植物の成長に重力はどう影響するか」「金属を溶かして固めるとどうなるか」など、地上ではできない実験が宇宙で行われました。
毛利さんはその後も2000年に再び宇宙へ行き、日本の宇宙活動を象徴する存在となりました。帰還後は日本科学未来館の初代館長として、子どもたちに科学の面白さを伝える活動を続けています。
一方、当時のNASDAは2003年にJAXA(宇宙航空研究開発機構)として再編され、人工衛星、ロケット、国際宇宙ステーション、探査機「はやぶさ」など幅広い分野で成果を上げています。「宇宙の日」はJAXAの活動と連動し、日本人が宇宙に夢を持つきっかけを提供し続けているのです。
宇宙の日の目的と意義
宇宙の日が持つ意義は、大きく分けて以下の通りです。
- 教育的意義:子どもや学生に科学への興味を持ってもらう
- 社会的意義:一般市民が宇宙を身近に感じられる機会を作る
- 国際的意義:世界の宇宙活動と連携し、日本の立場を示す
実際、文部科学省やJAXAは毎年「宇宙の日」に合わせて作文・絵画コンテストを開催し、数万人規模の応募があります。これらは単なるイベントではなく、科学リテラシーを育てる教育活動として高く評価されています。
国連の統計によれば、宇宙関連産業は今後も世界的に拡大し、2030年には100兆円規模に達すると予測されています。その中で、日本が人材を育成し続けるためにも「宇宙の日」は欠かせない存在なのです。
宇宙の日の歴史と関連行事
宇宙の日ふれあい月間とは
宇宙の日を中心に、9月は「宇宙の日ふれあい月間」として設定されています。全国の科学館、プラネタリウム、JAXA関連施設で特別イベントが行われ、来館者数が普段の2倍以上になることも珍しくありません。
代表的な取り組みには以下があります。
- 作文・絵画コンテスト
- 科学館での特別展示
- 宇宙飛行士や研究者による講演
- プラネタリウムの特別上映
特に作文・絵画コンテストは人気で、毎年1万人以上の応募があります。テーマは「未来の宇宙」や「宇宙でやってみたいこと」などで、子どもたちの自由な発想が表現されます。入賞作品は展示会で紹介され、多くの人に見てもらえるため、参加すること自体が誇りになります。
宇宙の日と世界宇宙週間のつながり
世界的に見ると、国連は「世界宇宙週間(World Space Week)」を毎年10月4日から10日に定めています。この期間は「人類初の人工衛星スプートニク1号の打ち上げ(1957年10月4日)」と「宇宙条約発効(1967年10月10日)」を記念したものです。
日本の「宇宙の日」は1か月早いですが、両者は補完的な役割を持っています。日本国内では9月の「宇宙の日」イベントで関心を高め、その流れを10月の「世界宇宙週間」につなげる形で活動が行われています。
実際、科学館では9月から10月にかけて「宇宙特集展示」が組まれることが多く、訪れる人に国際的な宇宙活動を紹介する機会になっています。
日本人が初めて宇宙に行ったのはいつ?
「宇宙の日」の制定理由になったのは毛利衛さんですが、実は日本人で初めて宇宙に行ったのは秋山豊寛さんです。
1990年12月、秋山さんはTBSの記者としてソ連のソユーズに搭乗し、宇宙からニュースを生中継しました。日本語での宇宙放送は世界的にも珍しく、大きな話題となりました。
ただし、秋山さんは「研究者」や「技術者」としてではなく「報道特派員」としての搭乗でした。一方、毛利さんは科学者として自国の実験を宇宙で実施した初めての日本人です。
この違いにより、秋山さんは「日本人初の宇宙飛行士」として記録されつつも、毛利さんが「日本の科学を担って宇宙に行った第一人者」として特別視されているのです。
宇宙の日のイベント・行事
作文・絵画コンテスト
「宇宙の日」に合わせて最も広く知られている行事が、作文・絵画コンテストです。文部科学省とJAXA(宇宙航空研究開発機構)が中心となり、小学生から高校生を対象に毎年テーマを設けて募集しています。
過去のテーマには「未来の宇宙開発」「宇宙でやってみたいこと」「宇宙と地球のつながり」などがあり、子どもたちの自由な発想を形にする機会になっています。例えば、宇宙で動物園を作りたいという夢、宇宙エレベーターで地球と宇宙を行き来する絵、月で植物を育てる研究の作文など、多彩なアイデアが寄せられます。
このコンテストの目的は、単に優れた作品を選ぶことではありません。宇宙を題材にすることで、子どもたちが科学や技術を「自分ごと」として考えるようになる点に意味があります。文部科学省の統計では、応募者数は毎年数万人規模にのぼり、科学系イベントの中でもトップクラスの参加率です。入賞作品は展示会や科学館の特別展で公開され、多くの人が目にすることでさらなる刺激を与えています。
JAXA筑波宇宙センターの特別公開
茨城県つくば市にあるJAXA筑波宇宙センターは、日本の宇宙開発の中心地のひとつです。「宇宙の日」や「ふれあい月間」には、普段は入れないエリアを公開する特別イベントが行われます。
主な見どころは次の通りです。
- 国際宇宙ステーション(ISS)日本実験棟「きぼう」の管制室見学
実際に宇宙飛行士が使っている装置や、地上からのサポートの様子を間近に見ることができます。 - ロケット・人工衛星の模型展示
実物大のH-IIAロケットの模型や、探査機「はやぶさ」のレプリカなどが並びます。 - 宇宙飛行士の訓練設備公開
無重力環境を模擬した訓練プールや、宇宙服を着用する体験も可能です。
この公開イベントには全国から数万人が訪れます。特に親子連れや学生に人気で、未来の研究者やエンジニアを志すきっかけになっています。
日本科学未来館の企画
東京都お台場にある「日本科学未来館」も、宇宙の日に関連した展示やワークショップを実施します。ここは毛利衛さんが初代館長を務めた施設で、宇宙をテーマにした常設展示が豊富です。
宇宙の日の時期には、次のような企画がよく行われます。
- 宇宙飛行士による特別講演
- プラネタリウムの特別上映(ISSから見た地球映像など)
- 子ども向けワークショップ(ペットボトルロケット作りなど)
日本科学未来館は年間100万人以上が訪れる人気施設で、科学を体験的に学べる場として国際的にも評価されています。宇宙の日は、その役割を最も強く感じられる期間なのです。
はまぎん こども宇宙科学館の催し
神奈川県横浜市にある「はまぎん こども宇宙科学館」は、通称「宇宙船のような建物」として知られています。宇宙の日には、子どもたちが主役となるプログラムが豊富に用意されます。
- 宇宙クイズラリー
- 天体観測会(望遠鏡で月や惑星を見る体験)
- 親子工作教室(宇宙望遠鏡の模型作りなど)
この施設は市民科学教育を目的にしており、地域に根付いたイベントを大切にしています。宇宙の日をきっかけに、科学が生活の中に根付く効果を狙っているのです。
岐阜かかみがはら航空宇宙博物館のイベント
岐阜県各務原市にある「岐阜かかみがはら航空宇宙博物館」も、宇宙の日に特別企画を実施します。ここは航空機と宇宙関連機材の両方を展示している全国でも珍しい施設です。
イベント内容の一例としては、
- 宇宙飛行士講演会
- 実物のロケットエンジン展示
- 宇宙服着用体験
- VRを使った月面探査体験
があります。航空と宇宙の両面から科学を紹介するため、他の科学館とは一味違った視点で楽しめるのが特徴です。
宇宙雑学・話題づくりに役立つ知識
宇宙はどれくらい広い?どんな形?
宇宙の大きさは「観測可能な範囲」だけでも直径約930億光年とされています。光は1秒で地球を7周半できるほど速いですが、その光でも930億年かかる距離です。
形については、宇宙全体は平らで無限に広がっているというのが現在の主流の説です。ただし観測技術がまだ完全ではないため、「宇宙は閉じている」「風船のように膨らんでいる」などの説もあります。
宇宙はどうやってできたの?
宇宙の始まりは約138億年前の「ビッグバン」とされています。これは宇宙が一点から急激に膨張した現象です。NASAやJAXAの観測衛星が捉えた宇宙背景放射(マイクロ波)によって裏付けられています。
つまり私たちが見ている星も、すべてこのビッグバンの名残の中に存在しているのです。
ブラックホールとは何?
ブラックホールは、強すぎる重力によって光さえも抜け出せない天体です。中心には「特異点」と呼ばれる無限の密度を持つ点があるとされます。
2019年には国際共同研究で、史上初めてブラックホールの「影」の撮影に成功しました。これは人類が想像だけで語っていた存在を、実際に確認できた歴史的快挙でした。
宇宙にも「地震」がある?
実は宇宙でも「地震」に似た現象があります。月面で観測される「月震」や、恒星内部で発生する振動です。NASAのアポロ計画では、宇宙飛行士が月に地震計を設置し、月が地殻変動することを確認しました。
地球以外に水のある星は?
木星の衛星エウロパや土星の衛星エンケラドゥスには地下に液体の水があると考えられています。NASAの探査機が氷の割れ目から噴き出す水蒸気を観測したことで裏付けられました。将来的には生命が存在する可能性があるとして、注目されています。
宇宙で最も冷たい場所・暑い場所
宇宙で最も冷たいのは「ブーメラン星雲」で、温度はマイナス272度。絶対零度(-273.15度)に近い極限の環境です。
逆に最も暑いのは恒星の中心部で、数千万度にも達します。太陽の中心温度は約1500万度です。
宇宙飛行士になる方法
日本で宇宙飛行士になるには、JAXAの選抜試験に合格する必要があります。条件は次の通りです。
- 大学卒業以上の学歴
- 自然科学系の知識や研究経験
- 身体的な健康と強靭な精神力
- 英語力(NASAなど国際機関と協力するため)
倍率は数百倍にもなり、非常に狭き門ですが、夢を持つ人は多く挑戦しています。
日本にいる宇宙飛行士の人数
これまで日本人宇宙飛行士として公式に認定されたのは12人です。その中には野口聡一さん、星出彰彦さん、若田光一さんなど、国際宇宙ステーションで活躍した人物が含まれます。
宇宙旅行がまだ難しい理由
近年は民間の宇宙旅行ビジネスが始まっていますが、費用は数千万円から数億円。最大の課題はコストの高さと安全性です。ロケットの打ち上げは莫大なエネルギーを必要とし、リスクも伴います。JAXAや民間企業は「再使用ロケット」などでコスト削減を進めていますが、一般化には時間がかかりそうです。
宇宙の果てはどうなっている?
宇宙がどこまで続いているのかは未解明です。現在の観測では930億光年の広がりが確認されていますが、その外側に何があるのかは分かっていません。「果てはない」「別の宇宙が存在する」など、多くの仮説が立てられています。
まとめ
今回は「宇宙の日 言われ」について解説しました。宇宙の日は、由来や目的を知ることで身近に感じられる記念日です。イベントに参加したり雑学を学んだりすることで、日常の会話や学びにも役立ちます。最後に記事のポイントを整理します。
- 宇宙の日は9月12日制定
- 毛利衛さんの宇宙飛行が由来
- JAXAや科学館でイベント開催
- 作文・絵画コンテストが人気
- 宇宙に関する雑学が豊富にある
宇宙の日をきっかけに、未来の科学や宇宙の不思議に一歩近づいてみてください。